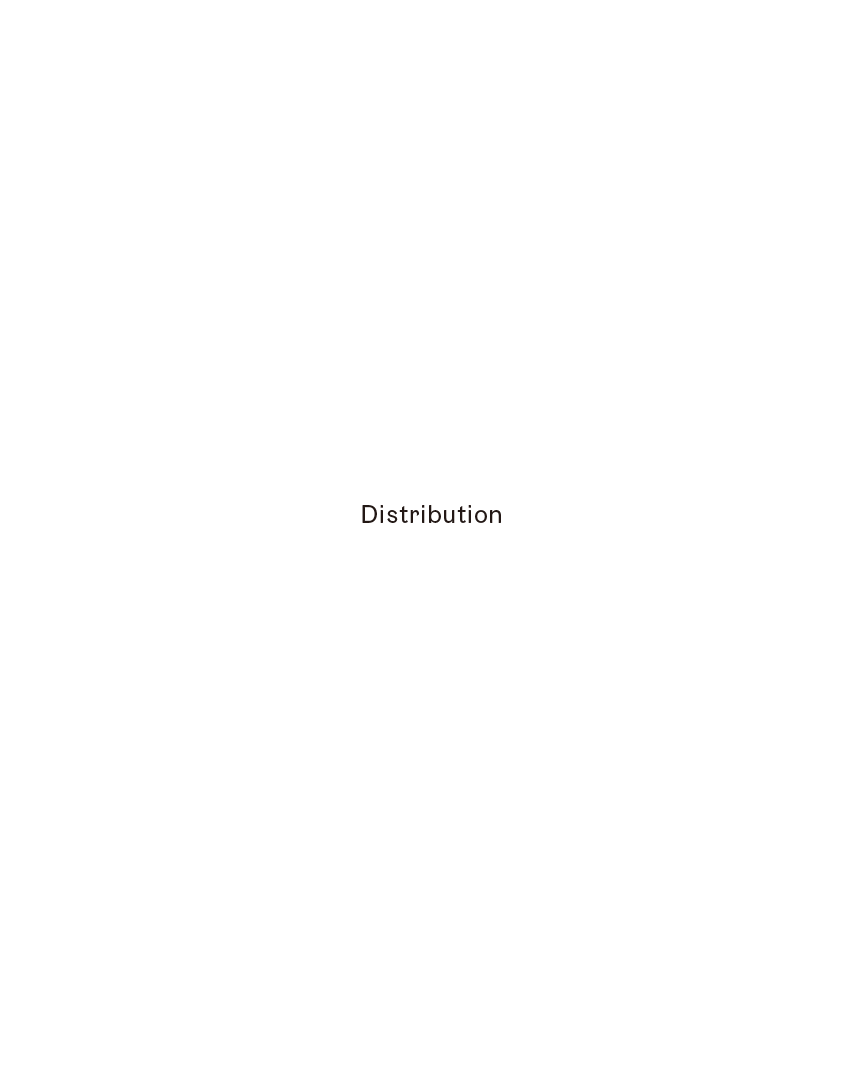監督や俳優へのインタビューで、「この映画のメッセージは何ですか?」と尋ねるのが、個人的に少し苦手だ。映画とは、観る側が自由に受け取っていいものだと思っているからだ。そこに流れている問いや思いのようなものを、それぞれが自分なりのメッセージとして解釈するのは構わない。けれど、つくり手がそれをことばとして提示してしまうと、とたんに「正解」のような効力をもってしまう気がする。映画には、まだかたちになっていない、いろんな人たちの思いや願いが無数に詰まっている。私は、そう信じているのだ。

『THE END(ジ・エンド)』
ジョシュア・オッペンハイマーが、1965年にインドネシアで密かに行われた100万人規模の大虐殺の事実と、その実行者たちが英雄として裕福な暮らしをしていることを知り、彼らに虐殺現場を演技で再現させた『アクト・オブ・キリング』。そして、被害者の弟アディが加害者たちを訪ね、対話を試みる『ルック・オブ・サイレンス』。彼が長編3作目として手がけた初の長編フィクションは、この2本のドキュメンタリーで投げかけられた問いを、別の形式でさらに追いかける作品だ。地下シェルターで暮らす富裕層の白人家族とその仲間のもとに、一人の若い黒人女性がやってくる。過去の自分をその罪ごと見つめることができる彼女は、かつてのアディであり、加害者たちにカメラを向けるオッペンハイマーのまなざしと重なる。歌うことで明日はいい日になると前だけを向くティルダ・スウィントンら演じる、表向きパーフェクトに見える家族は、アメリカン・ミュージカル的なポジティブ性の危うさを象徴する。目を背けたいものと向き合うことから、希望は地に足をつけて歩き出す。

『THE END(ジ・エンド)』
全国公開中
配給︓スターキャットアルバトロス・フィルム
©Felix Dickinson courtesy NEON ©courtesy NEON
https://cinema.starcat.co.jp/theend/

『小川のほとりで』
川の水の流れのパターンを織っているテキスタイルアーティストのジョニム(キム・ミニ)は、ソウルの女子大で講師として働いている。演劇祭を10日後に控え、外部の男子学生が恋愛スキャンダルで演出役から外されたことから、その穴埋めとして、有名演劇人の叔父シオン(クォン・へヒョ)が臨時の演出家としてやってくる。女子学生らもジョニム自身も、大きな流れのなかで揺れている。けれど、不安を抱えながらも対話し、手をつなぎ、ときには感情をぶつけ合う。監督ホン・サンスの撮る映画を観ていると、何も起きていないようで、ふと「いま、奇跡のような瞬間に立ち会っている」という気持ちにさせられる。なぜなら、ホン・サンスや登場人物として存在する俳優たちが身体で発見していく過程の感動が、そのまま伝わってくる気がするから。演劇祭が終わった後の打ち上げで、学生たちが「私がなりたいと思うのは……」と即興で詩を語る場面。そこであふれる正直で純粋な希望のことばに触れて涙がほおを伝ったのは、何歳であっても、「なりたい自分」を探し続けている自分を発見したからかもしれない。

『小川のほとりで』
2025年12月13日(土)より、ユーロスペースほかにて新作を5カ月連続で順次公開中
©2024 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved.
配給:ミモザフィルムズ
https://mimosafilms.com/gekkan-hongsangsoo/

『グッドワン』
17歳の少女サムは、父クリスと、父の旧友で売れない俳優のマットと共に、2泊3日のキャンプに出かける。両親の不仲や離婚の行く末を目の当たりにしてきただろうサムは、中年男性二人が浴びせる心ない発言やマウントじみた会話に呆れたりモヤモヤしながらも、彼らのやりとりに耳を傾け、間に立ち、ケアし続ける。彼女は間違いなく「いい子」であろうとしている。森を歩くなかで、父と娘、旧友同士、娘とその父の友人という三者の関係性は常に揺れ動く。現代を生きる10代の少女であるサムの振る舞いは、女性が担うことを期待され、また得意とされてきた役割を、いまもなお背負っているように映る。一方で中年男性たちもまた、老いゆく身体や過去への執着、コントロール欲といった男性性の規範を手放せずにもがいている。けれど、多くを語らないサムが、ある出来事を機に変化を見せる。脚本・監督を手がけたインディア・ドナルドソンは、葛藤を避けるのではなく、不快さやわからなさを体験することで生まれる強さと、新たな調和の可能性を示している。

『グッドワン』
2026年1月16日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町他全国ロードショー
©2024 Hey Bear LLC.
配給:スターキャットアルバトロス・フィルム
https://cinema.starcat.co.jp/goodone/

『君と私』
2014年4月16日に韓国で発生した、修学旅行中の安山市檀園高校の生徒250人を含む、304人が犠牲となったセウォル号沈没事故。修学旅行前日の1日に起きる物語だが、何が起きたかを知っている私たちは事故のことを想起しながら、彼女たちを見つめることになる。女子高生セミ(パク・ヘス)は、ハウン(キム・シウン)が死んだ夢を見て、彼女が入院する病室へと走る。修学旅行に行くことを諦めたハウンに、セミは一緒に行こうと必死で説得するが、秘めた思いを打ち明けられず二人はすれ違ってしまう。恋をし、不安になったり、暴走したり、泣いたり、浮かれたり。セミを取り巻く日常は、夢のように煌めいて映る。誰かを失いたくないと思ったり思われたりという感情の交流も、突然訪れる死も誰にでも起こりうる。君は私だったかもしれないし、私は君だったかもしれない。俳優チョ・ヒョンチョルの長編初監督作品は、想像することしかできない距離にいる私と、同じように生きていた君を重ねて、記憶をつなぐ。

『君と私』
渋谷ホワイトシネクイント他にて全国公開中
ⓒ2021 Film Young.inc ALL RIGHTS RESERVED
配給:パルコ
https://youandi-film.com/

『ブルーボーイ事件』
東京オリンピックや大阪万博で沸く高度経済成長期の日本では、国際化に向けて街の浄化を進めようと、警察が売春の取り締まりを強化していた。戸籍上は男性のまま、身体的性特徴を女性に変えて売春をする、俗に「ブルーボーイ」と呼ばれた人々は、売春防止法の対象外だったため、警察は彼女たちに手術を施した医師を、優生保護法(*現在の母体保護法)違反として逮捕し、裁判にかけた。法廷では、手術を受けたトランスジェンダー女性たちが、「幸せか不幸か」を延々と問い続けられることになる。自身もトランスジェンダー当事者の監督・飯塚花笑は、当事者の俳優をキャストに迎え、この事件を映画化。恋人にプロポーズされ、幸せを噛み締めていた喫茶店で働くサチ(中川未悠)は、弁護士・狩野(錦戸亮)から、裁判に証人として出廷してほしいと依頼される。本作は、矢面に立ち、変化を求めて声を上げた人々の声を過去として流さず、いまを映し出す鏡として提示する。自分らしく生きる幸せを潰されずにいられる社会へ向かうために。

『ブルーボーイ事件』
全国公開中
©2025『ブルーボーイ事件』製作委員会
配給:日活/KDDI
https://blueboy-movie.jp/
小川知子/Tomoko Ogawa
1982年、東京生まれ。上智大学比較文化学部卒業。雑誌を中心に、インタビュー、映画評の執筆、コラムの寄稿、翻訳など行う。共著に『みんなの恋愛映画100選』(オークラ出版)がある。
https://www.instagram.com/tomokes216