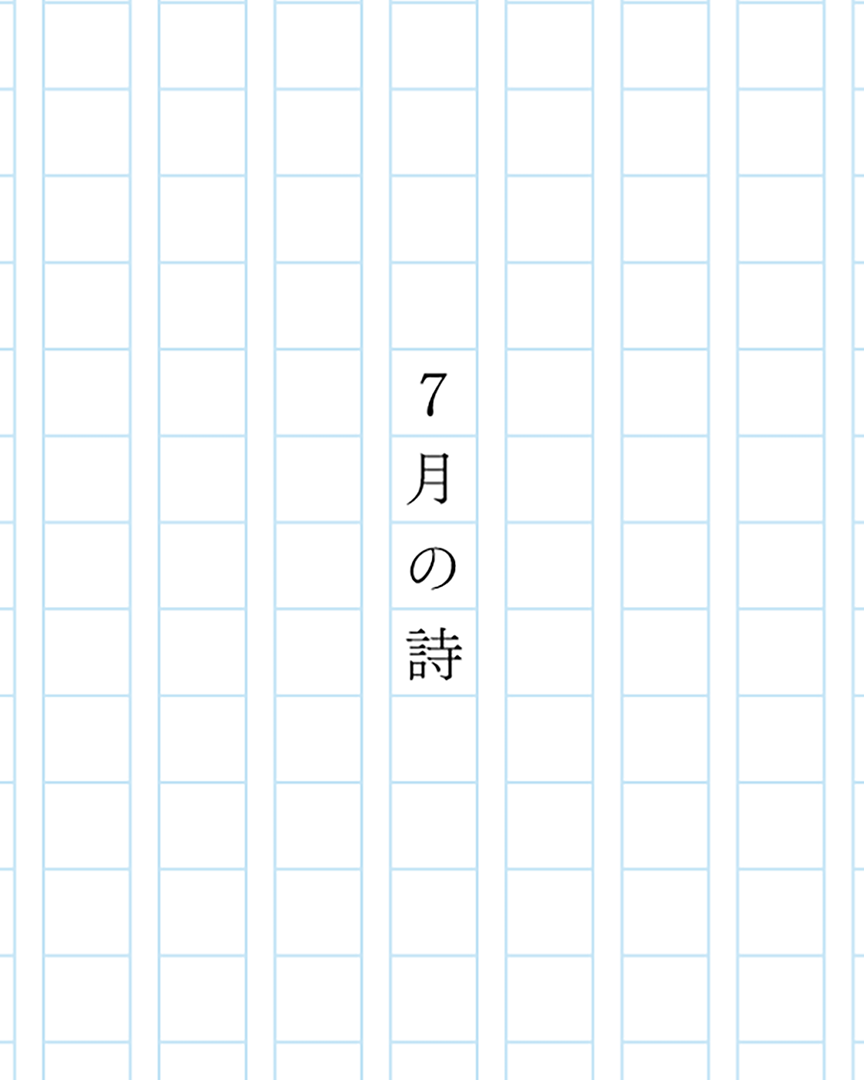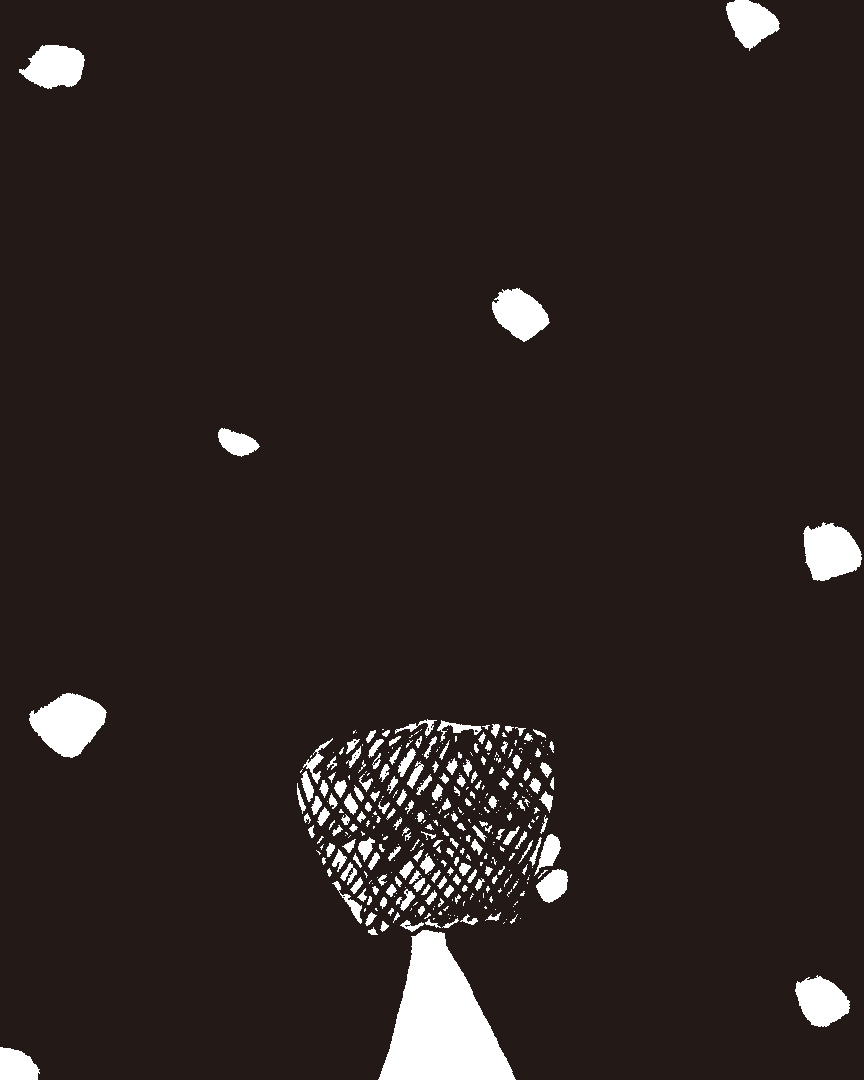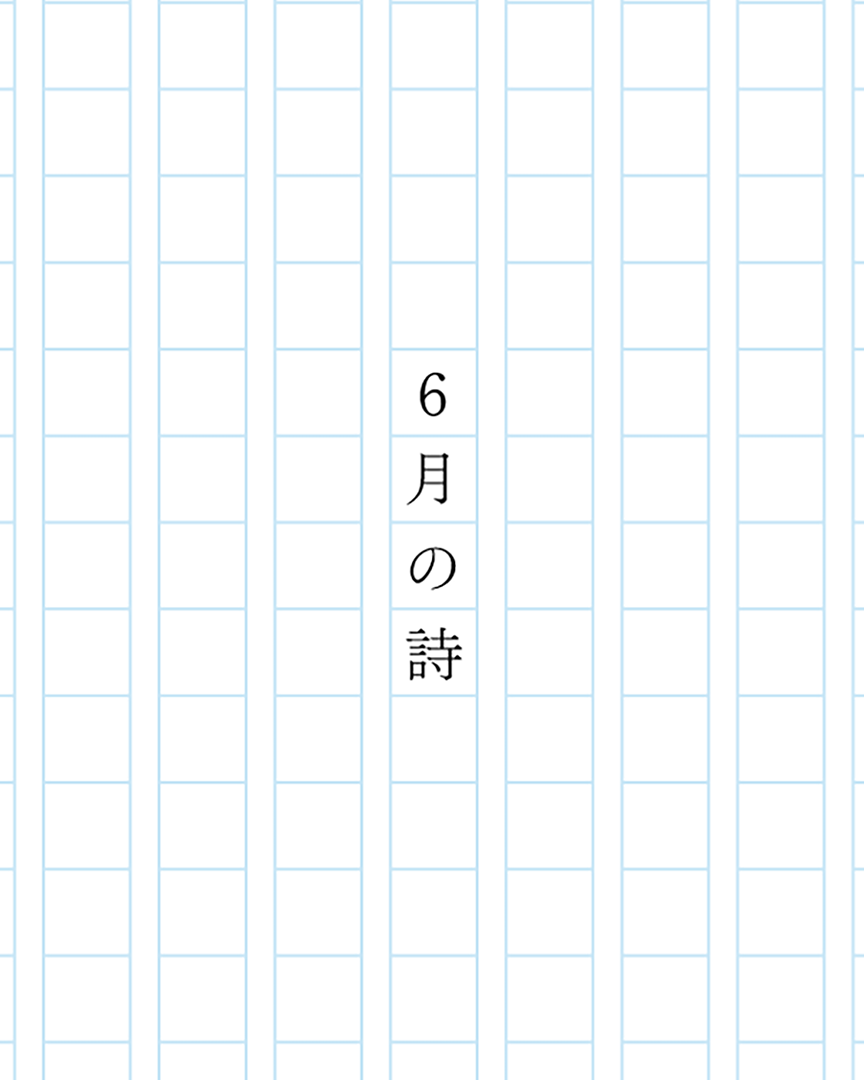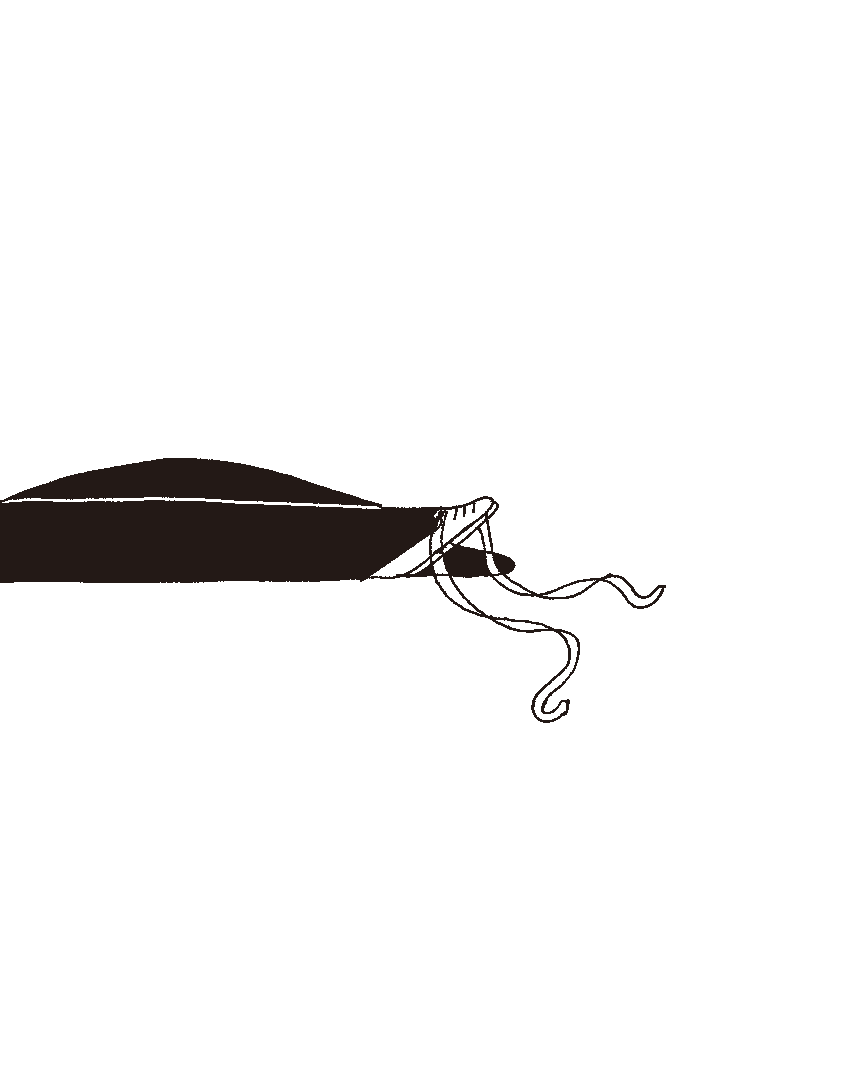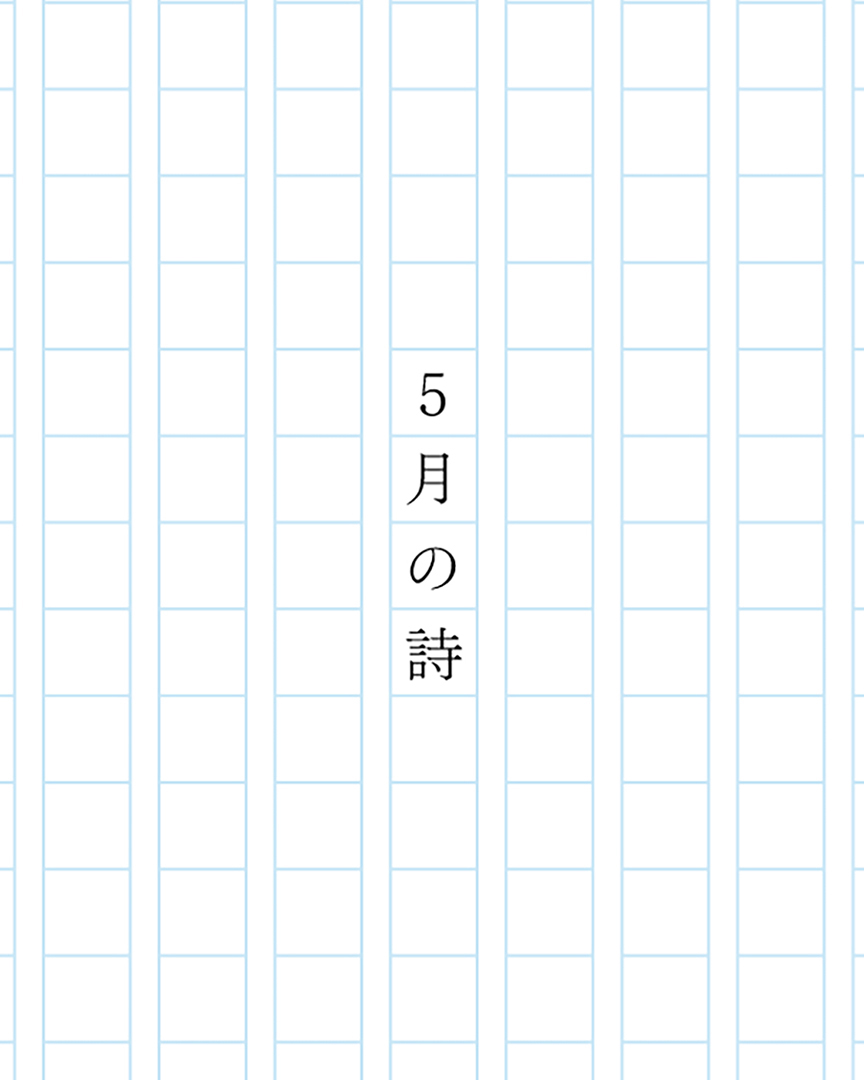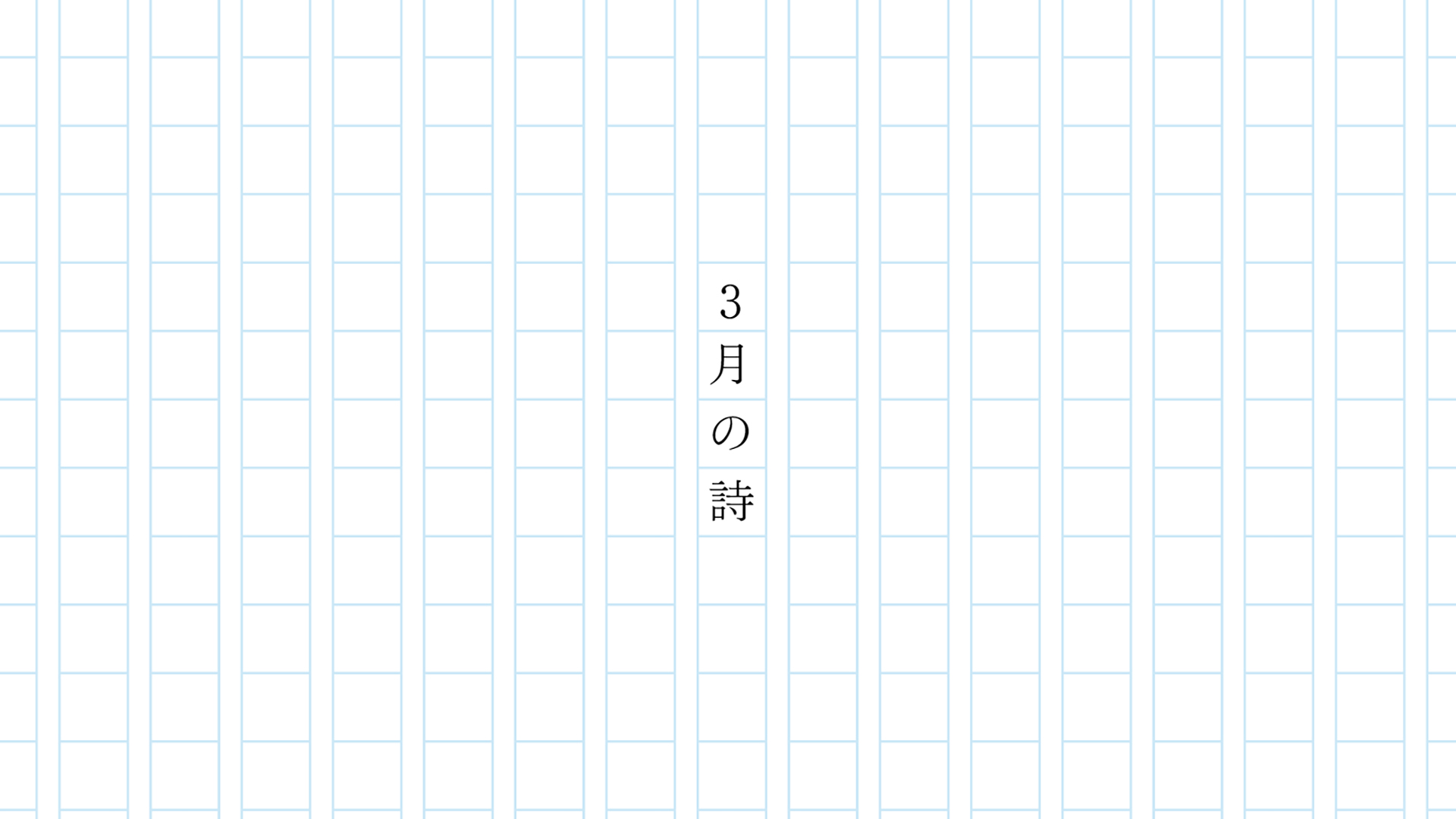
ことばになる前のものたちにふれることができる
ときにそれらはことばの周りにいたりする
砂鉄みたい、塵みたい、湯気みたいに、そこにいる
それらの気配を人間は、感じることができる
そういう器官をもっている
感じることが合図になる、あなたがそれにきづいたこと、わたしはわかる
わたしがわかったこと、あなたはきづく
そういうやりとりによって、
蒸気のような沫のようなことばの周りで、
みえかくれしていたものたちが、
かたちになっていく。
ふっと息をふきかけると、綿毛になってとんでいってしまう
ことばを発音してしまうと、ひゅっと、それにひっついて、影にしずんでしまうものたちが、
わたしたちの、とてもびみょうなニュアンスの、ささやかなやりとりによって、糸になる、
すこしだけ、すこしだけ、あまれていく
目の前で、
ふっと風につれさられてしまう、ほそい糸は、交互にあまれることで、
時間の中にうもれず、そこにのこる。変なあみめで、
そこにのこる。どうぶつの、いきづかい
あせ、小さなふるえ、
心臓の。そんなものたちが、ひとぬいひとぬいとなり、
ひとりでに、
あみめをつくる。はじまってしまう。
それが、
みえたらいいね。ときどきは。
ひかりの加減で、みえたりみえなくなったりする、蜘蛛の巣みたいな透明な、
雨がふったあとの朝のひかりに透かされて、
発見できるように、
そんな、あみめが、時にながされずに、のこるものとして、語りが、あったら、しらぬまに、あったら、
自分たちの庭先に、
ふっときづくとあったら、
雫をたたえて一瞬きらりとひかったら、
心強い。
とても。
ちぎれても、ところどころ、ほころびたりすることがあっても。
手でつかんでまるめてしまっても、それがあった、
その営みがあった。ひとりでに、いることで、はじまってしまう、
やりとりの中で、ささやかな、息づかい。あせ、小さなふるえ、
心臓の。あせ。うぶ毛がひかる。子犬の腹の。
それらが、そのすべてが、
糸となり、別の糸とひきあい、
時間の中にうもれることなく、
ささやかな、
あみめになるということ、
それが、
みえたらいいけれど。
みえなくてもいいね。もう
わかったね。
記憶の中にしまわれる、
朝の庭先で、忘れられたようにある、
雫をたたえた透明なくもの巣が。
ひかりの加減できらりと、ひかったり、
みえたり、みえなかったり、
する。
あった。
それでいいって。
宇宙船の搭乗口で思い出す。
髪の毛を後ろで結びながら。
選評/暁方ミセイ
この作品はよるのさんの詩論かもしれません。言葉にすることによって切り捨てられてしまうものたちを憂いながらも、それらが人間のあいだでは、完璧にとらえることはできなくても存在として伝わることを見つめています。本当に伝えたいこと、表現したいことは、使う言葉のまわりやあいだにあるのです。そして人間は、それを読み取ることができる。語り手は、そのことを希望とともに胸に抱いて、地球を(きっと、この世という言葉ある懐かしい故郷を、いつか)去っていきます。
最初の一行目で「ことばになる前のものたちにふれることができる」と高らかに宣言しているけれど、実際にはこの詩は、当たり前ですが言葉でできています。やわらかな言葉たちは、発した肉体を感じられる声のようで、体のなかにしまわれている思いへと遡りながら、同時に言葉でしか表すことのできない新しい世界を読み手の前に広げていきます。
となると、「ことばになる前のものたち」というのは、単にそれを表現する人物の思いだけではなくて、言葉それ自体の伝達としての役割を背負う前の姿のことも含んでいるように思えてきます。自由な言葉たちと踊ることこそ、詩の醍醐味ですよね。