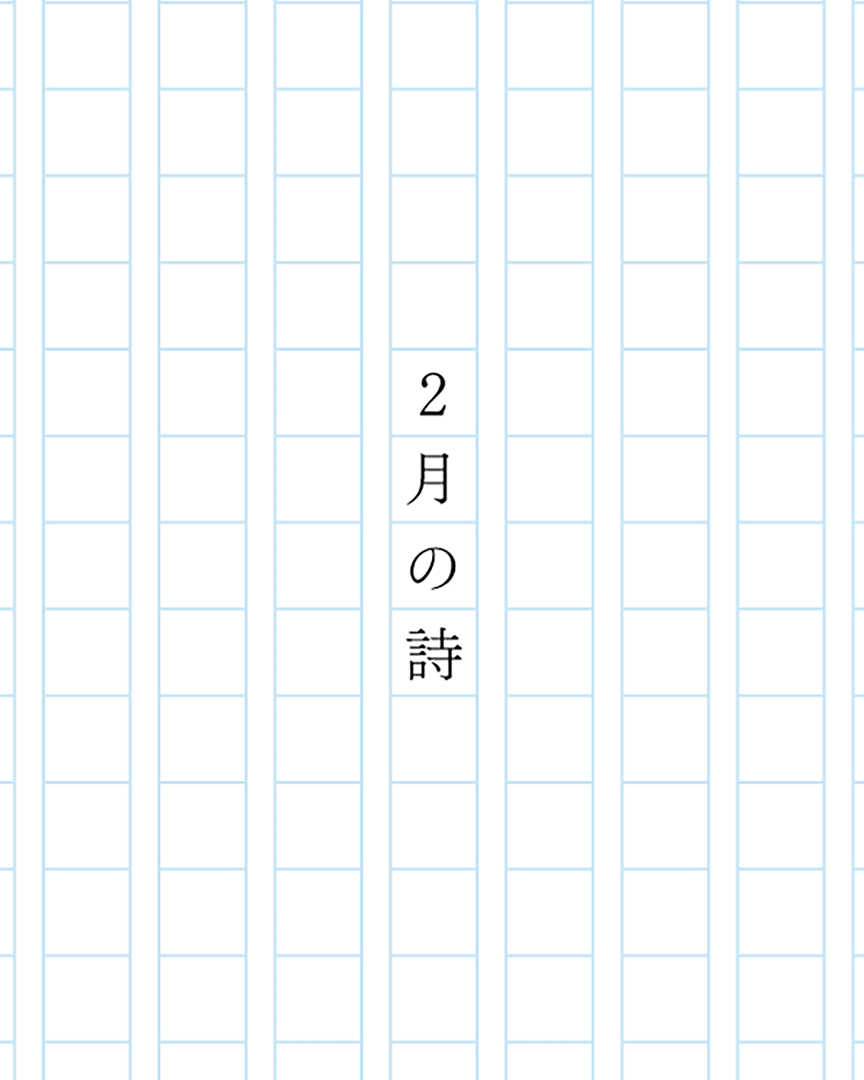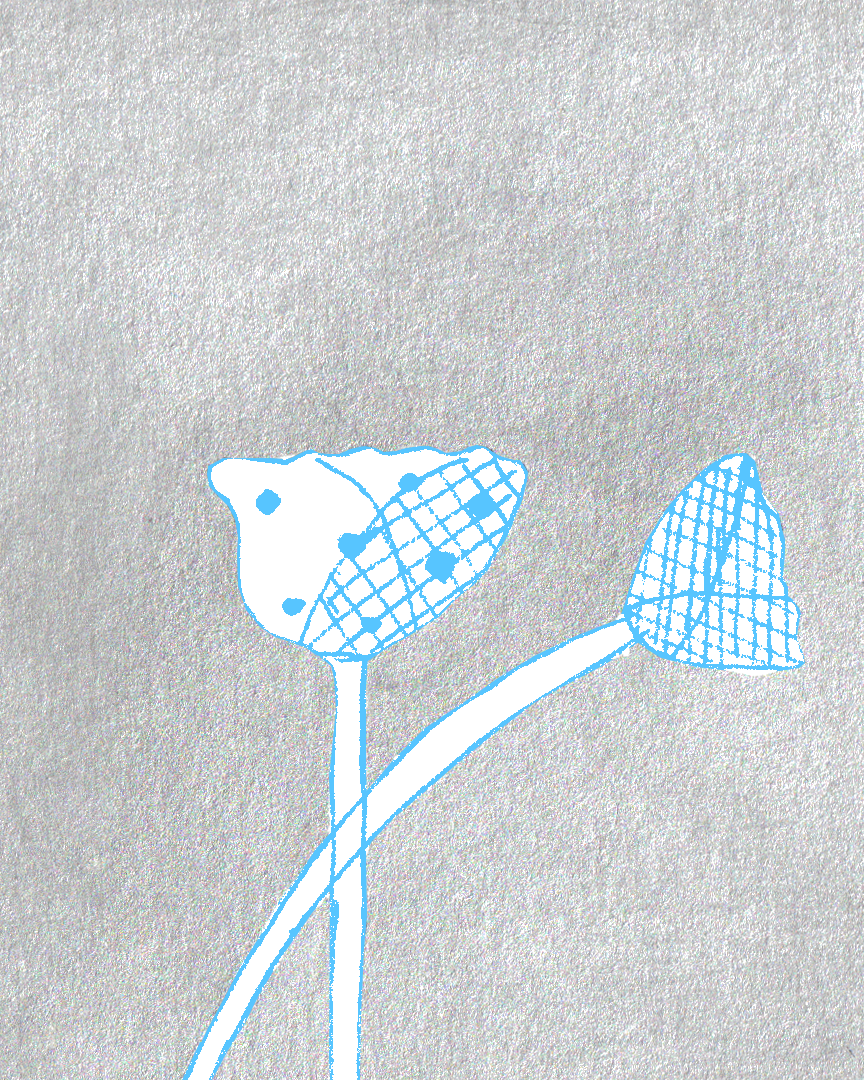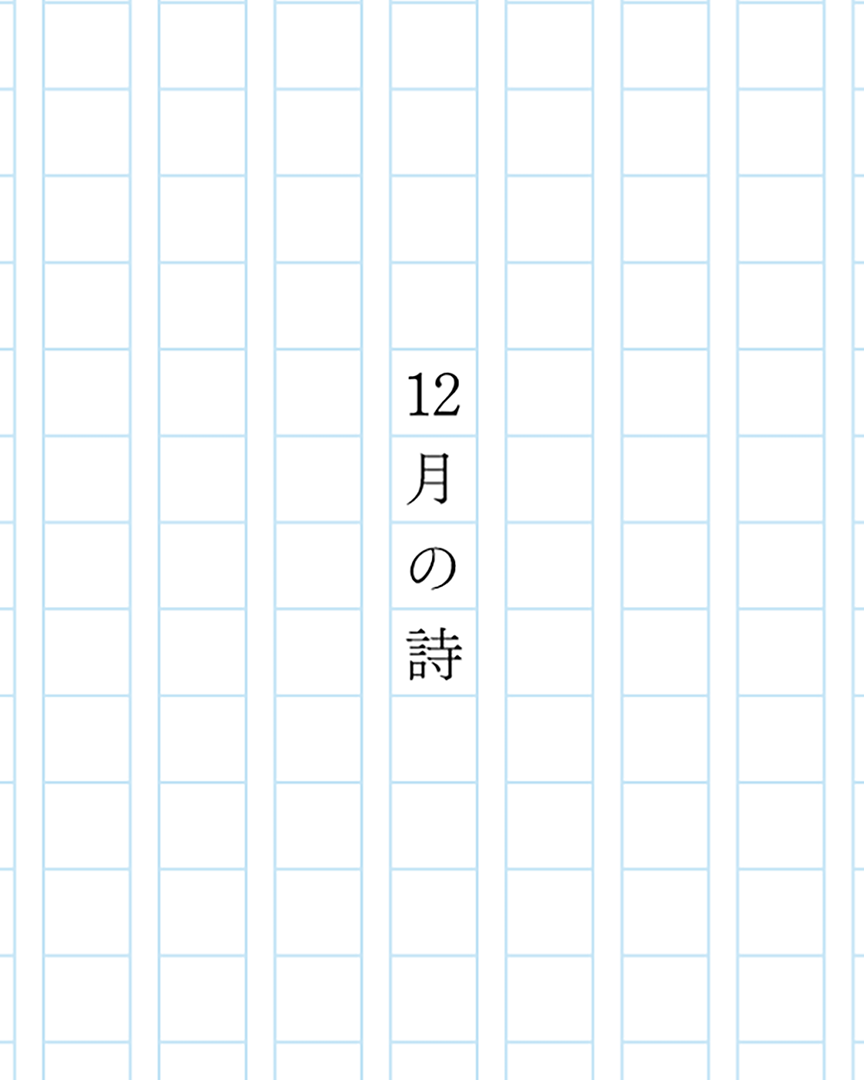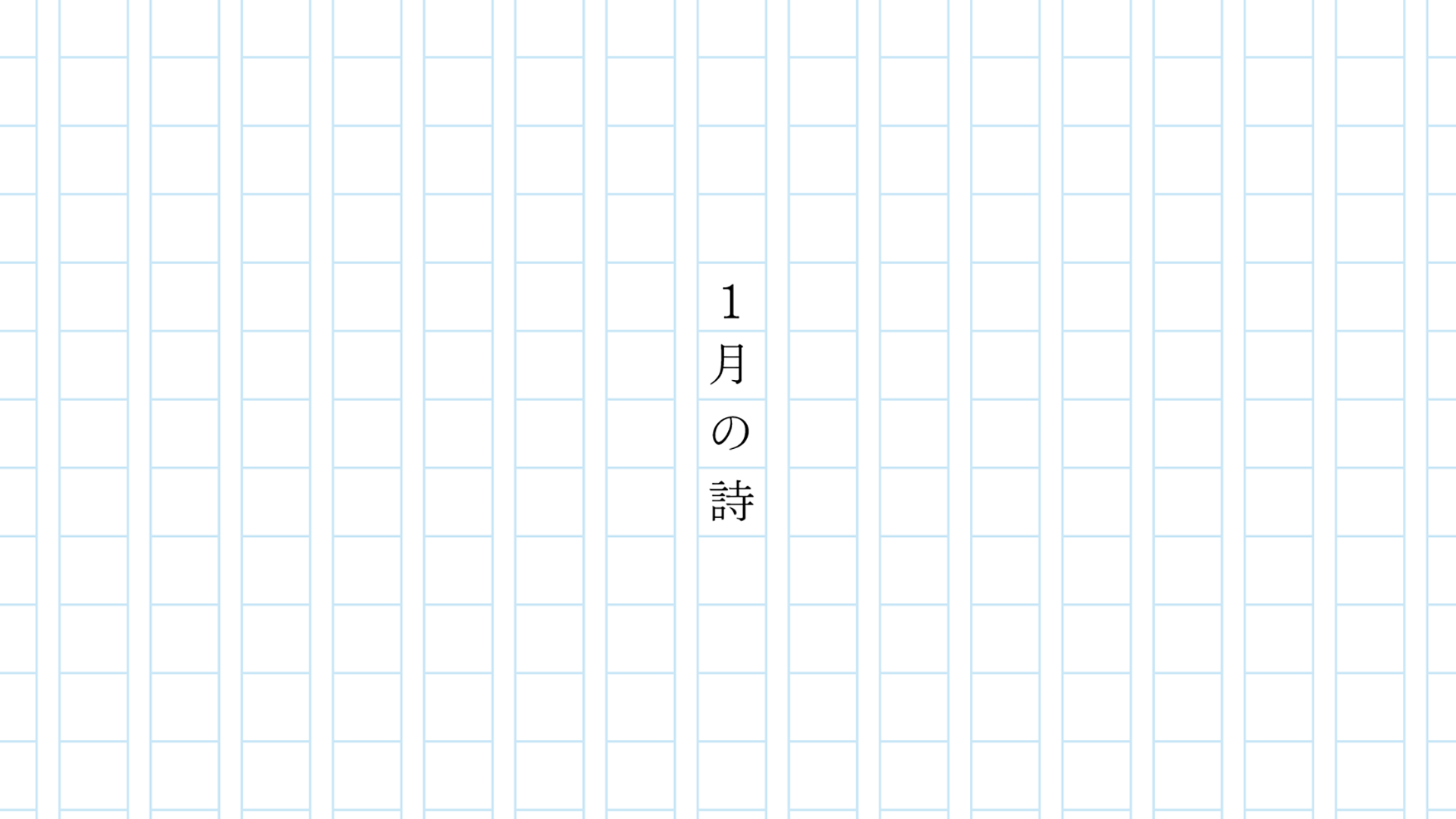
詩を書くくらいしか
もはやできもしない指で
欲するはいちリットルばかりの
アイスクリイム
方形の寝床に暮らす隠遁者は 若くして
冷たく老いて 枯れていく魚
赤い小さな灯りだけを点した部屋の
レースのかかる窓にきく雨音は遠く
水は別の町に降る
見知らぬ町は水に沈み 魚の家も
にわか漂う方舟 こころよい孤独
こころよい解脱 空箱に魚は暮らす
パンの欠片を色気なく食む
塩の味がうっとうしいから
つよいコーヒーの麻痺を吸う
辞書と古い小説の掠れぎみのインキを
ほほえんで愛する
オリーヴ油をノートに溢し
鉛筆の文字は震えて滲み
聖書を書き写すのにも丁度いい
ツァラトゥストラかく語りきと
魚は目覚め 発狂を演じる
旅人にも成れず 住人の身分を得られず
食むべき苔を判らず 棲むべき水を判らず
空箱に魚は眠る
心臓は空箱
血はきっと透明に違いない
鰭は偽物 鱗を剥がし
現るは肉 肉なき肉 骨と膿
学者連は困って 名無し魚の命名を
先延ばし 薬漬け、燻製にした
硝子に小さなラベルが巻かれる
「異端あるいは不具者」
魚は学者を観察して言った
まことにこのように言った、
「これらは賢いひとびとだ」
またこのように。
何もかもを判っているし、
完全な理性を持っているもの。
すばらしい社会宗教を創りあげたし、
過去と未来を殺すことで、愛を、
肉の命を絶つことで、
新しい無機的生命を活かすことだけに
熱狂していられるのだ。
すばらしい発明家だなあ
魚は飽き飽きして
あるいはまったく満足して
足と手を切り落とした
舌を取り去り 目をえぐり出し
臓物を吐き出したあと
重い鱗の外套を着て
鰭を縫い込んだ
むかしに描いた絵の
やさしい黄色と紫の川辺
芝はよく乾いている
魚は芝に身を横たえて
指の名残を思い出し
なにかを愛する仕種をした
選評/環ROY
ニーチェは『ツァラトゥストラかく語りき』において、世界にはそれを最終的に支える意味や真理が存在しないことを描き出した。
ツァラトゥストラ(編注1)の語る超人は、普遍的な真理や固定された自己を前提とせず、人間の脆さや構造への依存を抱えたまま、世界の無意味と向き合う主体である。世界の無意味さや不完全さを自由の条件として引き受ける、前向きな絶望としてのニヒリズムは、絶えず変化する状況のなかで思考を止めない誠実な知性の一形態であり、現代においても有効である。
この詩をそうした観点から読むと、ほとんど寓話のようにも読める。魚は詩人や芸術家、あるいは子どもたちを思わせ、無機的な生命はAIを連想させる。頻出する方形のイメージはベッドや集合住宅、都市、モバイルデヴァイスを、水に沈んだ町はモニターの向こう側を想起させる。呆れ果てて外へ出て、寝転がり、指の感覚へと戻ってくる終わり方も物語的だ。
ニーチェの主張を踏まえ、現代社会の生活感覚を詩に変えることで、結果として寓話になったのかもしれない。しかし物語であることは、詩であることを否定しない。むしろ強いリリシズムを備え、知的な興奮を喚起する哲学的な詩として立ち上がり、ヒエロニムス・ボス(編注2)の絵画を眺めているような感覚が残った。
編注1:『ツァラトゥストラかく語りき』におけるニーチェ自身の思想を表現するために用いた作品の主人公の名前。
編注2:15〜16世紀ネーデルラントの画家。寓意的で幻想的な絵画により、人間の欲望や世界のあり方を描いた。